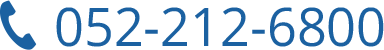1.日本人の宗教観はいい加減
あなたは、仏教を信じますか、神道を信じますか?
外国人からこんな質問を受けると、戸惑ってしまう。そこで、両方ですと答えると、”神道と仏教は同じような宗教ですか?”と又質問されてしまう。
日本人の宗教は、神道なのか仏教なのか判然としないので、日本人の宗教観はいい加減という人がいる。
ところが、実はこのいい加減さが日本人の宗教観の本質であり根が深いのだ。
日本国内の神道の信者は、8,396万人、仏教の信者は7,076万人(令和4年12月文化庁調べ)で、両方足すと日本人の人口をオーバーする。
困ったことに、”無宗教です”と答える人も多く、これを足すと人口の倍では効かない。
何故こんなことになったのかというと、神仏習合が影響している。
神といっても日本の神さんは一つではない。八百万の神であり、仏もそれに匹敵するぐらい多い。多神教同士が習合したのでかなり複雑だ。
「神仏習合」、「本地垂迹説」という言葉を聞いたことがあると思うが、仏教伝来以前の日本人の宗教は、アミニズム(原始宗教)或いは祖先崇拝の民間信仰で,教義がないので宗教とは言えないという説もある。
しかしその見方はヨーロッパ人からするとそう思えるのだろう。「教義のない宗教は宗教ではない」と定義すれば、神道は宗教ではない。
アイヌの宗教と日本人の祖先崇拝の宗教に共通性が多いとする説もある。
アイヌ民族の宗教には、人間のみならずあらゆる動物が死ぬと、霊が天に還ると信じられている。この宗教観は、縄文時代からあったらしい。カミという言葉はアイヌのカミ「カムイ」からきているのかもしれない。
邪馬台国では、死者を葬ったのち、家族の者は水中に入って禊(みそぎ)を行っていたようだ。ユダヤ教徒が体を清めるのに似た、禊という宗教的沐浴の歴史は古く、主としてそれが海水で行われた。
古事記にも、黄泉の国から戻ったイザナギが海水で禊をしたと記されている。
海から遠い人たちは、海水を竹筒に保存して使ったが、長期間保存すると水が蒸発し塩が残る。この塩がお清めになった。
葬儀などから帰って家に入る時、お相撲さんが土俵に「塩をまく」のは穢れを払う清めの儀式で、古からの風習が今も残っている。
ここで大事な点は、この当時は死後の魂(霊魂)の存在を信じていたことだ。
日本人は、神が天にいるとか、人が死んだら星になるとかいう信仰は全くない。神は天にはいなく、山・川等地上にいるので、星座に関連する神話がない。
日本人は、神をどう捉えていたのだろう。神は、「全知全能の神」という意味ではないことは確かだ。だから、神は欧米人が考えているようなGODではない。政権の中枢をお上(オカミ)、川の上流をカワカミ、天皇が住まわれた御所の中心地をカミガタと云うから、上なるものを指す場合と、人知を超えた能力を持つ風神・雷神も神と呼んだ。
動物も、人間にとって脅威となるものは神に祀り上げられた。ヘビは形からしても気持ちが悪い。マムシに噛まれると大変になることは誰でも知っている。だからヘビを神として祀っているところは多い。また古代は狼に襲われることもあったので、狼は神、それも大きなカミ(大神)だった。
それでも、天地を創造したGODと異なり、日本の神は、自然と人間との間で共生しており、まことに身近な存在である。
神は、自然であったり動物であったり、生活を営むために人間を助けたり、災いをもたらしたり、人の死後に神になったりする。
自然信仰、民族信仰、祖先信仰で、仏教が輸入される以前は、日本人の民族宗教であり、神と人間を結ぶために祭祀が行われた。祭祀が行われた場所が神社であり、そこは聖域なのである。
神社と寺院の決定的な違いは、
寺院は、修業のために僧侶が生活する場所でもあり、そこに商人が入り寺院を中心とした街が形成される。だから、寺院は人のための場所で、人の生活の匂いがする。
寺院は、仏像を安置するために建物が必要だった。本堂・金堂・講堂・僧侶が学ぶ宿舎・食堂・宿坊を備えると、大掛かりな伽藍になる。僧侶の数は、神社の神職の比ではない。維持費も大変だ。だから、拝観料を必要とする寺がある。
仏教は、本来煩悩(心の迷い)を取り払うものであったが、平安時代に入ると救いを対象としたため、阿弥陀の世界を求めて大量に寺院が建築された。
一方、神社は神のための場所で、その聖域には結界(鳥居)があり、そこに入る前に一礼する。結界を過ぎると精神潔斎をするために、口をすすぎ、手を洗う。
神道には本来、拝殿・本殿はない。建物が建てられたのは仏教の影響である。
だから、本殿のある神社にカミは常駐していない。閉じられた空間だけがある。そのため参拝客は、柏手を打ってカミを呼ぶのである。
大事な点は、神道には救済という概念はない。家内安全・交通安全・商売繁盛・結婚相手が見つかりますよう、というような「生」の領域を担当する。
七・五・三、上棟式・地鎮祭・結婚式等、ハレの行事は神道の領域である。
又、神社は聖域だから、拝観することを念頭に置いていない。参拝のために訪れることを前提にしているから、拝観料は取らない。
現在、八幡神を氏神とする八幡神社と天満宮が多い。八幡神社は、戦国時代に多くの武将が亡くなり、殺された者達が祟りをなすと信じられ、鎮魂のために建てられたことと、清和源氏が八幡神を氏神としたことによる。
八幡神は、応神天皇だと云われている。この八幡神は、宇佐から奈良にやってきて東大寺大仏殿の大仏を守護する神となった。
宇佐から石清水、そして鶴岡まで勧進されたことで全国展開された。
天満宮は、菅原道真の怨霊を封じ込めるために建てられた。
藤原時平の陰謀で、菅原道真が流罪になり死に追いやられた。彼の怨霊により清涼殿に雷が落ち、藤原家の人々が次々に亡くなったので、その魂を鎮魂するために建てられたのが天満宮である。
菅原道真は、学問の神様とされていることから、京都だけでなく全国に建てられた。
神道は、元々「生」の領域だけを担当していたわけではなく、「生」と「死」の両方を担当していた。そもそも、「もがり」(遺体を安置しておくための儀式)は神道用語である。(例、もがりの宮)
仏教伝来以降、特に平安時代に阿弥陀信仰が盛んになって、「死」の領域を仏教が担当したことによる。
欽明天皇以前の天皇は、政治上の統治権と国の祭祀を司る最高権力者であり、神々の直系の子孫として正当性が付与されていたため、神(先祖)を祀る重要な職務があった。
天皇が生前に天皇と呼ばれるのは近世のことで、それ以前はすべて「院」と呼ばれ(白河院、後鳥羽院)、死後におくり名として天皇を付していた。天皇とは、死後の天上界での称号だったからカミ(神)となったのだろう。
天皇家は、神々の直系の子孫を継承することが何より重要な仕事であり、崩御すれば神となる。神道は、「生」と「死」の両方の儀式の領域を担当していた。
但し、後醍醐天皇のように生前に天皇と呼ばれた例外はある。
538年に百済の「聖明王」が欽明天皇に仏典と仏像を授けたことから、この年に仏教が伝来したとされている(日本書紀では552年)。
何故、欽明天皇の時だとされているのか、よく解からない。
仏教が伝来したとされる538年は、欽明天皇ではなく第28代「宣化天皇」のはずなのに。
「宣化天皇」は536年に即位し、僅か3年後の539年3月に亡くなっている。その年、539年12月に欽明天皇(「宣化天皇」の弟)が即位している。どちらでもいいことだから、ここでは深く追求しない。
この時天皇は、仏教を国家の宗教として認めるべきか否かを群臣に問うた。
物部・中臣の両氏は、天皇は神祇官のトップであり、神話時代以来の統治権とその正当性を継承するものであるから、国家宗教として認めるべきではないと反対した。
一方、蘇我氏は、朝鮮半島との繋がりを重視し、”仏教を取り入れるべきだ”と主張し、両者は「一歩も譲らないぞ!」と頑なになった。そこで戦争になってしまった。
聖徳太子は、母(穴穂部間人皇女・・あなほべの はしひとの ひめみこ)が蘇我氏の血統(蘇我稲目の娘)だったので、仏教を取り入れざるを得ない立場にあったことと、何より自身が仏教に深く帰依していたことで、仏教輸入に対し積極派だった。
戦いは、当初は物部氏が優勢だったが、太子が戦勝を祈願し「勝ったら四天王を祀る寺を建立する」と仏に約束したことで勝利したことになっている。
蘇我政権は、物部氏に勝利したのだから、本来であれば神道から仏教に乗り換えてもよかったのだが、聖徳太子は「和を持って貴しとなす」という考え方だから、神道を排斥したわけではない。
この考え方が神仏習合の原点だったのだろう。
蘇我派の聖徳太子は、約束通り戦勝を祈願して大阪の天王寺に「四天王寺」を建てた。
四天王とは、東西南北に神を配置して、仏を悪魔からボディガ-ドをする神のことで(因みに、釈迦のガ-ドマンが仁王様「金剛力士」である)、四天王が同時に安置されているのは、この「四天王寺」と法隆寺金堂だけだ。
東:持国天
西:広目天
南:増長天
北:多聞天(毘沙門天)・・・・四天王のリ-ダ-
仏教の神は、仏・如来のボディーガードとしての役割に過ぎない。
587年、聖徳太子の父用明天皇は「仏教を信じ、神道を尊ぶ」として和解させた。しかし、全く合わない神道と仏教を取り入れれば、国家観がなくなってしまう。
仏教は、百済からの輸入であったが、元は中国仏教である。
隋と唐の時代まで、日本は遣隋使、遣唐使としての留学僧、留学生を送り込んだ。この時学んだ中国仏教は、既に純粋仏教ではなく、道教や儒教思想が混入しており(三教合一論)、日本に輸入されると更に神道が加わることになる。
それでは、日本の統治者は、生まれも育ちも全く異なる、仏教と道教・儒教と神道をどう取り入れ、調和させたのか。
平安時代からは、仏(本地)が衆生を救うために姿を変えて(神)、この世に現れた(垂迹)と考えられた。(これを本地垂迹説という)
これによって、日本古来の神々は仏の下に位置付けられてしまった。
神は仏の権現(仏が人々を救済するために、神の形になって地上に出現すること)とされ、日本古来の神々は仏の権現とされた。
例えば、熊野権現(スサノオ、イザナギ、イザナミ)、春日権現(春日大明神)、徳川家康(東照大権現)も権現とされた。
もっと極端に言うと、仏の本地はインドで、大日如来が伊勢に垂迹して天照大神になったという説である。こうすると、神仏は簡単に一体化してしまう。そうなると、天皇の祖先は仏ということになり、比叡山に日吉大社があり、奈良の興福寺に春日神社があってもおかしくない。
寺は、〇〇山〇〇寺(比叡山「延暦寺」、高野山「金剛峰寺」)と云うように、山が先で寺が後になっている。これは元々、山に神があり後から仏が山に居候したので、山が先になったという説(梅原猛説)がある。
奈良仏教は市街地で栄えた仏教だから、山号はない。最澄と空海は山に本拠地を置いたので、山号がついたのは平安時代以降だろう。
日本人は、聖徳太子の「和」の思想が今日まで、我々の心に深く染みついている。この考え方が、神仏を対立させることなく、神仏習合という日本独自の宗教観を定着させた。
大日如来は、如来の中の如来で、太陽のようにあまねく世界を覆っている如来なのである。盧舎那仏(ルシャナブツ)が究極の形に発展したのが魔訶(マカ)盧舎那仏であり、これが大日如来だと思えばよい。東大寺の大仏は、魔訶盧舎那仏だ。それが天照大神となったと解釈することにより、神仏を一緒にリスペクト出来たわけである。
このアイディア以外に、神仏を和解させる方法はない。
古代の日本人は、「和」の天才だったと思う。
中山恭三(なかやま きょうぞう)/不動産鑑定士。1946年生まれ。
1976年に㈱総合鑑定調査設立。 現在は㈱総合鑑定調査 相談役。
著書に、不動産にまつわる短編『不思議な話』(文芸社)を2018年2月に出版した。