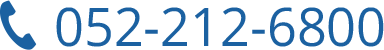3.怨霊信仰
平安末期から鎌倉時代初期の貴族は、末法思想(終末思想)に恐れおののいていました。
末法思想と云うのは、釈迦入滅後、500年から1,000年が正法(正しい釈迦の教えが普及している)の時代。
1,000年から1,500年は像法(形だけ正しく、悟る人がいない時代)、1,500年から2,000年は末法(仏教が衰退し、釈迦の教えだけ残り、修業も悟りも得られなくなる)時代のことです。
釈迦が入滅したのは、BC486年ですから、平安時代後期は末法の始まりにあたり、1,052年頃から始まると考えていました。
桓武天皇は、既存勢力が横暴になった「南都六宗」の仏教と決別したかったこともあり、奈良から京都に遷都し、仏教を大きく変える必要を感じていました。
桓武は、そこで都を京都に移すと、空海と最澄を中国に行かせ、唐で最新の教えとして流行していた密教を取り入れました。
奈良仏教からの決別をした桓武天皇が、最澄・空海を登用して密教を取り入れたことは、顕教から密教への移行であり、何よりも小乗仏教から大乗仏教への大きな転帰となりました。
特に奈良仏教を大きく転換させた最澄の功績は、その弟子の法然が、阿弥陀の世界へと民衆を導く浄土宗の基礎を作り、更に一般民衆にも理解できるように簡素化しました。その後、親鸞によって浄土が民衆の身近な存在となったのです。
仏教に、「国体護持」、「鎮護国家」を期待したのは奈良時代と同じでしたが、「国体護持」、「鎮護国家」は、本来、国家権力が担うものであり、仏教にそんな力はありません。
当時の日本は、皇室は跡目争い、貴族は権力闘争、民は飢えと病気が蔓延し、治安が悪かったので、罪のないものが殺され、死んでいきました。それでも天皇は、国家を維持しなければなりません。
ところが、桓武天皇は治安維持より、怨霊封じ込めに異常と思えるほど熱心でした。
その理由は、桓武天皇の後継を、父である光仁天皇から桓武の弟の早良親王にするよう命令されていましたが、息子(後の平成天皇)が生まれてしまったのです。彼は、我が子可愛さに何の罪もない弟を殺してしまいました。だから、弟の祟りを恐れたのでしょう。
そこで、天皇は国体護持と怨霊の鎮魂を仏教に期待しました。南都六宗(奈良仏教)は、本来、国体護持と怨霊の鎮魂とは何も関係がない教えなのです。だから、役に立ちません。そこで、この目的のために最澄を唐に留学させたのです。
ところが、天皇の意にかなう仏教を持ってきたのは、期待されていない空海でした。空海が唐から持ってきた密教は、加持祈祷を中心とする呪術的なものだったので、天皇には怨霊封じ込めはこの密教しかないと思ったのでしょう。
護摩を焚き、あの強面の不動明王の仲介のもとに呪文を唱え、時々『喝!』と叫べばいかにも効果がありそうです。
残念なことに、本来、仏は霊の存在を認めていませんので、怨霊封じ込めは出来ないのです。
桓武天皇は、弟の怨霊が何時自分に襲い掛かってくるのか、眠れない夜が続き、霊に取り憑かれ過ぎていったのです。
新しい都は、外部から怨霊が都に入らないよう、風水(陰陽道)で固め、下鴨神社・神護寺・将軍塚・松尾大社を建て、この四つの地点の交差部に内裏を建てました。
更に、鬼門にあたる北東方に延暦寺、裏鬼門にあたる南西方に東寺を建て、最澄と空海に怨霊を封じ込めさせたのです。
更に桓武天皇は、死体から怨霊が出る恐れから、死刑制度を廃止して最高刑を流罪、又、人間の死を極端に恐れたことから、軍事力まで放棄してしまいました。
密教は人間そのものが仏であるので、その仏性に気づけば誰でも仏になれると説く教えで、曼荼羅は、この世界の実相を表現したものです。
従来なら「現実世界の中で、成仏を目指して修行を続ける」と考えていたのですが、密教は曼荼羅に描かれているように、「修業を続けるからこそ、現実世界がこのように現れてくる」と考えるのです。
護摩を焚くことは、「あの世とこの世」、「人と仏をつなぐこと」で、怨霊を鎮めることではありません。
薪能、お盆の迎え火、送り火は、火によって霊魂を迎えたり送ったりする役目をします。この火の媒介者が不動明王なのです。
天台宗は比叡山に、真言宗は高野山に寺を建てましたが、天皇が求める鎮護宗教でも、怨霊封じ込めの宗教でもありません。
天皇家を始めとする皇室、貴族、民衆が最も恐れたのは、怨霊のほか、病気や災難で、それから自分を守ってくれる術を仏教(密教)に求めたのです。この需要に答えたのが真言宗なのです。
この宗教は、
①国家を鎮護する
②病気を治す
③呪われた怨霊を追い払い、逆に呪術を使うことによって相手を呪い殺す
等が可能だとしたことから、皇室との関係は出来たが、庶民との距離は遠かったのです。
密教は、その神秘性や不可解さが強く人々を惹きつけました。当時の人々は理解しがたい病気や災難を、「物の怪にとり付かれた」と考え、物の怪からの解放を加持祈祷に求めたのです。ですから、当時、真言宗の僧侶はお高く留まっていました。このことを皮肉ったのが吉田兼好の「徒然草」です。
この時代は、幼児死亡率が高く、天然痘を始めとする病気で死亡するものが多かったのですが、死亡原因がわからないので、それを悪霊(物の怪)のせいだとするのは無理もありません。
肉体から悪霊を追い出せば、病を治すことが出来ると信じていました。
当時、「山川草木悉皆仏性」。全てのものには仏性があると信じていたのです。
本来の仏教は、山川のような無機の物体まで仏性を内包している考えは、ありえません。しかし人間にだけ魂があるという証明もないのですが、人間は死ぬと、肉体と霊魂が分離されると信じていました。
いや、今でも信じている人は多いと思います。
今はこんなことしませんが、昔、テレビが急に映らなくなると、テレビの横腹を叩きました。叩くことによって接触不良が改善されるから、たまに映るようになりました。
人間も死ぬと、肉体と魂の分離を抑えようとし、息を引き取る寸前に、或いは死んでしまった死者の名前を激しく呼ぶ「魂呼び」は、現在も、宗教とは無縁の人でも行っています。
分離しようとしていた魂が、肉体に戻るかもしれない期待感があるからです。テレビと違い、魂を呼び戻すには時間がかかります。
その時間が「もがり」なのです。だから、死んだらすぐに土葬或いは焼却はしません。一定期間、死体(肉体)から離れた魂が、肉体に戻ることを期待したのです。
死後、魂はそんなに遠くには行っていないはず。ひょっとすると、鴨居に留まっているのかもしれません。昔は、魂が鳥によって天に運ばれると信じられていました。
鳥葬や風葬が行われるのはこのためです。鳥が死体をついばみ、魂を天に運んでくれる。鴨居は、鴨(鳥)がそこに一旦留まると信じて付けられた名前なのです。
神社の鳥居も同じです。神社で鳥(鶏)が飼われているのは、鳥が宅配便の役割を持っているからです。
しかし、この世に恨みを残して死ぬと、成仏しないから肉体と霊魂がうまく分離されません。
無念の死を遂げた人は、簡単に仏にならないのではないかという考え(成仏しない)がありました。殺された死霊が、恨みを抱いてこの世をさまようと信じられていました。
殺された人やその遺族、冤罪によって刑務所に収監された人にとっては、怨霊や生霊となって真犯人を呪い続けます。真犯人はたとえ、刑を逃れることが出来たとしても、刑に服する以上に恐ろしい呪いを抱えて生きていかねばなりません。
この恐怖心が怨霊信仰を生んだのです。
「番町皿屋敷」、「四谷怪談」のような幽霊は、成仏出来ない肉体と霊魂がこの世をさまようのです。
怨霊は出る前に祀らなければなりません。もし、怨霊が出てしまったら鎮魂する必要があったのです。この役目は、本来神道のものでしたが、効き目がなかったのか、平安時代に入ると仏教(最初は、密教)にとって変わられたのです。
仏教は、「自分が死んだ」ことに気づかない故人に、”あなたは亡くなりましたよ”と諦めさせ、亡霊にならないよう引導(最後通告)を渡します。
本来、釈迦の教えは無神論に近く、「空」とは「無」のことで、「人間は死んだら終わりであり、消滅して無に還る」というのに近いのです。
空とは何もないのでなく、物はあるが総ては永遠のものではなく、必ずいつかは消えて行くという意味です。
西洋のことわざに「天は自ら助くる者を助ける」というのがあります。
善行を積み、奉仕活動をし、たっぷりの愛を他人に注いだとしても、天国に行ける理由にはなりません。
「人間の幸・不幸はDNAと運で決まる」と言えば、真理だと思いますが、これでは身も蓋もありません。
自分の無力さ・苦しみから救われるには、神に委ねるしかありません。
不条理な人生を歩んでいる人だけではなく、人間は誰もが弱い存在ですから宗教が必要なのです。
あなたは、人間が死ぬと肉体と霊魂が分離すると信じていますか。
「仏教の一派に、死んだら霊魂が別世界に行く。死体は亡骸なのだから、川に捨てようが、野に捨てようが一向に構わない」という考えがあります。
この考え、平安時代から普及していたようです。
その証拠に当時は火葬でもなく、土葬でもなく風葬だったのです。
京都には、「鳥部野」、「蓮台野」、「化野」(あだしの)という三大風葬地がありました。
「鳥部野」は清水寺の南西にある鳥辺山墓地だと思われます。高台寺、建仁寺、六波羅蜜寺がある辺りで、ここに六道の辻(道)があり、ここが「あの世とこの世の境目」で六道珍皇寺(ちんのうじ)があります。
この辻から南があの世とされています。
この寺には井戸があり、昼は官吏、夜は閻魔大王の裁判の補佐をしていたといわれている「小野篁」(オノノタカムラ・・・大男だったらしい)が、この井戸を使って地獄へ出入りしていたと云います。
当時、遺体は都の外に運びましたが、鳥部野は、三大風葬地の中で一番規模が大きかったようです。
源氏物語の桐壺、更衣、葵、夕顔がここに埋葬されたらしいのです。
風葬は、カラスやハゲワシに食べさせていたから鳥葬でもありました。
清水寺は、日本で最初の征夷大将軍、「坂上田村麻呂」のゆかりのある寺です。「十一面千手観音菩薩」を御本尊とする寺院で、音羽の滝の清らかな水にちなんで清水寺としたようです。
近くの鳥辺野は、死体が野晒しであったので、匂いがあまりに強いため、本殿は高い所に建てました。清水の舞台が突き出しているのは、ここから死体を投げ捨てるためだったのです。
「蓮台野」は、金閣寺の東にある小高い船岡山で、平安京はこの地を起点に造営されたことで有名です。
奈良時代は、薬草園と狩りの地で、生薬や染料に使う紫草(しそう)が生えていたところから、ここは「紫野」(むらさきの)と呼ばれていました。
船岡山の手前に、閻魔前(エンママエ)町があります。ここから北はあの世の入り口で、死者は、ここを起点にあの世に入ることになります。
船岡山の西を南北に走る「千本通り」は、平安朝時代、全長17km、幅85mあったそうです。九条通りから南は鳥羽街道と呼ばれています。1本しかないのに千本とは、死者を供養するために、千本(千とはとてつもなく多いという意味。例;千手観音)を超える卒塔婆が並べられたからこの名がついたそうです。
紫式部がこの地で余生を過ごし、紫野に墓が作られたから「紫」という名前だったとする説もあります。
金閣寺の近くに衣笠山(きぬがさやま)があります。ここは「蓮台野」の背後にあり、「蓮台野」に風葬された遺体に掛けられた着物、帷子(カタビラ、一重の着物・・・葬式で棺の死体に着せる死装束)、布綿が風で舞飛び、次々に山の木の枝にいっぱい引っ掛かっていたから「衣笠」と呼ばれたようです。
嵯峨野にある「化野」(アダシノ)のあだしは、悲しい、儚い(はかない)という意味です。ここも風葬が行われていました。
空海は、風葬された遺体を哀れに思い、ここに放置されていた千体の遺骨を埋葬し、石仏と堂を建てました。これが「念仏寺」で、空海の頃は真言宗でしたが、鎌倉時代、法然により浄土宗に改められました。
現在、境内に8千体の石仏が並んでおり、お盆に千灯供養が行われ、石仏に無数のロウソクが揺らぐ様は異様で圧巻です。
風葬は庶民だけに行われたのではありません。桓武天皇の息子である嵯峨天皇の皇后「橘嘉智子」(檀林皇后と呼ばれた)は、非常に美しく、僧侶の憧れとなっていた方で、「自分の死後は、亡骸を埋葬せず、どこかの辻に捨てて鳥や獣の餌にして下さい」と遺言をしたためました。
彼女は、自分の遺体が朽ちていく様子を九段階に描かせ(九相図)、遺言通り嵯峨野に捨てられました。65歳でした。
捨てられた場所は、京都嵐山線「四条大宮」から2つ目の駅、映画村で有名な「太秦広隆寺駅」の次の駅「帷子ノ辻」駅付近だと云われています。
京都で、「野」がつく地名の殆どは風葬の地だと思われます。
何故なら、既述したように、死体には霊がなく亡骸(単なる物体)だと考えていたからです。もう一つの理由は、平安時代に墓を造ることが出来るのは、三位以上の貴族だけで、庶民には許されていなかったためです。
風葬の地は京都郊外で、当時、郊外は「洛外」と呼ばれ格下扱いされていたようです。京都の仲間として対等に扱ってもらえなかったようです。
現在でも、洛内の人は洛外の人を京都人だと呼ぶことに抵抗があると聞きました。
風葬の習慣は長く続きませんでした。風葬地は、強烈な悪臭を放っていたので、死骸は土葬にして埋葬したほうがよい。又、葬式をして供養してほしいと考えるのは庶民だけではなかったはずです。
中山恭三(なかやま きょうぞう)/不動産鑑定士。1946年生まれ。
1976年に㈱総合鑑定調査設立。 現在は㈱総合鑑定調査 相談役。
著書に、不動産にまつわる短編『不思議な話』(文芸社)を2018年2月に出版した。