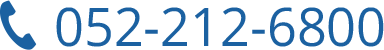2.神道から仏教への転換
「自然信仰」とは、神が鎮座する山・森の領域で、磐座・森林・神木・鎮守の森・神体山・夫婦岩・那智の滝等を「神奈備」(かんなび)と言いました。
神社の社、鏡、剱等の人工物は、縄文以降のご神体ですから、本来の神道信仰にはありません。
だから古い形式の神社には、拝殿はあるものの本殿は無いのが普通なのです。諏訪大社の前宮も、本来は本殿がなかったはずですから、後に造られたのでしょう。
日本の神道は、イエスや釈迦のような創始者はいません。だから創始者の像が存在しないのです。
例外は権現(人が神になった)ですが、人神祭祀は、菅原道真・平将門・豊臣秀吉・徳川家康を祭神とする神社がありますが、江戸末期までは例外的で、明治以降は、明治天皇や軍人が祀られるようになりました。
神道は、人を神として祀ること自体自由でありますが、キリスト教(カトリック)は、教皇に決定権があり「列聖の儀式」がなければ聖人にはなれません。
「祖霊信仰」の起源は、縄文時代の古代人の埋葬からある程度推定できます。人が死ぬと魂は肉体から離れ、里山のような「神奈備」に行くか、天に上るかどちらかと考えていたようです。死者には、花や土偶を一緒に埋葬し冥福を祈ったと考えられています。
一方で、死霊は恐ろしいものだと考えていたようです。
埋葬する際に、手足を折ってバラバラにして埋めたのは、魂が帰ってくるのが恐かったのだろうと考えられます。石を抱いて埋められている死体もあります。魂が死体に戻った時、手足がないと自由に動けないと考え、石を抱かせた死体もあります。
死霊が恐ろしいものだと思ったことがあります。
学生の頃、級友たちと一泊二日で琵琶湖に泳ぎに行った時のことです。近くの旅館で夕食をすませ、風呂から部屋に帰ると、中居さんが布団を敷いていました。
21時を過ぎていました。遠くで「コ-ン、コ-ン」と音がするのです。何の音だろうと中居さんに聞くと、棺の四隅を木槌で打っている音だと言うのです。
この地方ではまだ土葬だったので、「霊が棺から外に出ないように塞いでいるのですよ」と説明してくれました。この地方には、こんな習慣があったのかと本当に驚きました。
ところが後になって、地元の人からそれは逆だと聞きました。
「棺の死体から霊が出るのではなく、外から霊が入らないように」という儀式だと言っていました。
棺から霊が出るのと、霊がその死体に入るのとどちらが怖いのでしょう。
どちらも怖い話ですが、後者は、霊が肉体と結びついて棺を壊し、この世をさまようと考えれば後のほうが気持ち悪い。幽霊はこれではないかと思ったのです。
明治時代になると、死者の魂は一旦家の鴨居にしばらく留まり、やがて聖なる里山に行きます。死後の魂は鳥に運ばれて、あの世から戻った霊は茄子で作った馬で山に送り届けるのです。祖先の霊は、里山にいらっしゃるので、すぐに里帰り出来る身近な存在です。ですから、あの世とこの世を行ったり来たりするらしいのです。
しかも、祖先の霊は永久に里山にいるのではなく、近々、妊婦を通してこの世に生まれ変わるとされています。
昔は寿命が短かったせいで、おじいさん、おばあさんの顔をめったに見ることが出来ませんでした。物心つく頃には、祖母・祖父共に他界しており、祖先の霊になっていました。
あなたは、こんなこと言われたことはありませんか。
成長するにつれ、”おじいさん、おばあさんにそっくりだわねえ、生まれ変わりかしら”。
そう、先祖の霊は妊婦を通して、生まれ変わるのです。科学的にも、遺伝子を引き継いでいることからすれば、何年かすると祖母・祖父に似るのは何ら不思議なことではありません。最近までは、生まれ変わるというより「よみがえる」と言っていました。
「黄泉(よみ)の国」(あの世)から帰ったと言う意味です。
たとえ、生まれ変わらなくても、祖霊は年に2回、我が家を訪れてくれます。
縄文時代以降、長年にわたって信じられてきた自然信仰(祖先信仰)が、日本人に親しみやすく、受け入れられやすいのは当然です。
祖霊信仰は、自然の神と共にご先祖様が子孫を見守ってくれているという信仰です。本家に行くと、先祖の人達が見守ってくれるよう、遺影を和室の天井から吊るし、長押し(なげし)に立てかけるように並べてあるのを見たことがあるでしょう。
霊がこの世に戻るのは、お正月とお盆の時だけです。お正月には、我が家に戻る先祖の霊が、「迷わないように」と家の前に門松を立てます。昔は、松でなくモミの木でした。
昔は各家庭で門松が異なっていました。ス-パ-で門松を買うと、隣近所の門松が同じになり先祖の霊が迷ってしまうので、何か我が家の特徴を付け加えるとよいでしょう。
又、正月と盆は先祖の霊が帰ってくるので、家族中で先祖の霊と一緒にご飯を食べます。共食は祖先と子孫の絆を強くするので、出掛けてはいけません。
正月と盆は祝日でもないのに、日本中が一斉に休みをとりますが、日本の祝祭日は「ハレの日」のお祝いなのです。生存している人を中心に定められていますので、死者を迎えるという日を祝祭日とすることは出来ないのです。
しかし、先祖の霊が帰ってくる正月と盆は、国民の休日より重要な日なのです。年二回しか帰ってこないのですから。
それなのに、休みだからと言って出掛けては、ご先祖様に申し訳がありません。
年二回では少なすぎる。「もっと増やしてみてはどうか」。
お彼岸にご先祖様の霊が帰ってくることにすれば、2回増えるのではないか。
そのためかどうか解りませんが、お彼岸に祖霊を迎えるようになったのは、桓武天皇の御代に始まったのです。
いずれにしても、あなたが現在生きていられるのは、ご先祖様のお陰なのだということを忘れていませんか。
古代の人は、地上と天は「橋や柱で結ばれていた」と考えていました。
神々は、雨の浮橋(虹)を渡って人間の世界に降りてきました。その橋が「天橋立」なのです。
「丹波の風土記」によれば、「天橋立」は天に向かって直立して立っていたと記されています。イザナギは、これを使って天に昇って行きましたが、神様が眠っているうちにその橋が倒れ、地上に細長く横渡ってしまったのだそうです。
「能」では、あの世とこの世を結ぶ「橋掛かり」というのがあります。
柱は、神自体ではありませんが、神が宿っているという意味で使われています。だから、神様の数は、一柱(ひとはしら)、二柱(ふたはしら)と勘定します。
諏訪大社の御柱祭りは、この世とあの世をつなぐ柱ではなかったのでしょうか。
仏教は538年に百済の「聖明王」が、欽明天皇に仏典と仏像(釈迦仏の金剛像一体)を授けたことから、この年に仏教が伝来したとされています。
長野市にある善光寺の逸話にも、【538年、百済の「聖明王」が欽明天皇に仏教典と仏像を授け、天皇はそれを蘇我氏に預けた。ところが、この後疫病が流行し多くの人が死んだ。】と記されています。
この逸話によりますと、物部・中臣の両氏は、仏像の祟りだとしたため、蘇我氏は難波の堀江に仏像を捨ててしまいました。これを信州の本田善光が発見すると、仏像は”信州まで運んでくれ”と言ったのです。
本田善光は、仏像の言う通り、伊那の自宅に持ち帰って安置しました。これが飯田市郊外の「元善光寺」で、仏像はその後、長野市の善光寺「牛にひかれて善光寺参り」に移されたのです。
善光寺のご本尊の「一光三尊阿弥陀如来」(阿弥陀如来と観世音菩薩・大勢至菩薩)は、日本最古の仏像(日本書紀による)のようです。
善光寺は、仏教伝来前に既に百済系の人々が建てていました。宗派が分派する前にできたので善光寺には宗派がありません。それどころか、当時、女性は救いの対象外とされてきた(ジェンダ-・ギャップ)仏教の中にあって、善光寺だけが女性の信仰を積極的に受け入れていたのです。
現在は天台宗と浄土宗の二派が運営しています。
ここ、信州・信野の国は、大国主が出雲を追われて諏訪に逃れてきたので、出雲大社と諏訪大社は親子関係にあります。
その証拠に、諏訪には大国主のほか、コトシロヌシ・タケミナカタを祭神とする神社が多いのです。
大和朝廷(弥生系)に追われた縄文系の人々は、日本海を利用し出雲から諏訪に逃げ延びましたが、ここ信州・信野の国も弥生系の人達に攻められています。
シナ(朝鮮語・・・旗を立て、許可なく入るなという意味で、要は縄張り)がいっぱい作られ、最終的にシナ野の国(信野の国)として、大和朝廷に組み入れられた経緯があります。
弥生系の人達は、支配地を拡大しながら混血して行った際に、双方が多神教のためなのか、日本の土着の宗教と仲良くやってこられたので、日本固有の信仰に仏教が浸透して広めていったのでしょう。この経緯は、諏訪大社の縁起に詳しく書かれています。
神仏習合の起源が感じられます。
儒教が広く知れ渡る以前、中国にも建国神話がありました。
ところが中国では、建国神話より政治・戦争に興味があり、論語は「怪力乱心を語らず」(君主は怪力・乱心等の怪しい情報を語ることはない)として、非論理的なものとして語られることがなくなったようです。
一方、朝鮮には「檀君神話」があり、建国神話として広く知られただけでなく、日本にも伝えられました。
天武天皇は、日本も朝鮮を見習って建国神話が必要性だと感じ、日本書紀・古事記の編纂に取りかかりました。今までの日本の神道は、自然信仰・祖霊(御霊)信仰中心でしたが、天武天皇以降、神道は「皇祖霊信仰」を加え三つの神道系になったのです。
天皇は、自分が神の子孫であるから,統治権者として相応しく、血統による統治が次世代にも及ぶとする論理が必要としたのでしょう。
欧州と中国は、統治者の後ろ盾に神との関係性を持ちません。
キリスト教は、当初ロ-マ帝国に弾圧されましたが、やがてロ-マ帝国の信頼を得るために、地上は世俗の国王が支配し、教会は霊の救済(神の王国)を担当することで、役割分担したのです。
分担によって国王の地位は安泰となったので、国王は教会を庇護し、信仰を擁護しました。教会自身も国王に戴冠することによって双方が権威を高め合い、統治に協力することによって、神と国王がうまくやっていけたのです。
近代憲法の「政教分離の原則」は、元はといえばこれが起源なのです。
但し、ビザンチン教会は、皇帝が総主教を兼ねる体制なので、皇帝教皇主義が伝統となります。
英国教会は、国王が聖公会の総主教を兼ねていますが、「君主は、君臨すれども統治せず」として政治に関わっていません。
中国の皇帝は、儒教に基づく天を崇拝し、天から政(まつりごと)を預り、天を後ろ盾にして自分は天子、皇帝として君臨していたのです。
儒教時代の中国は奴隷制で、諸侯は家内奴隷を抱えていました。
男性の家内奴隷を「臣」、女性を「妾」と言います。
諸侯の「臣」は権力を振るい始め、権力欲しさに、自発的に臣になって諸侯に仕える者も出てきます。これを「官」といいました。
「臣」、「妾」、「官」の言葉の起源がここにあります。
皇祖霊信仰は、卑弥呼の時代から神を頼りに政治を行ってきましたので、起源はシャ-マニズムだったのかもしれません。
祖霊と同じく、霊は形で表すものではないし、皇祖霊に至っては形で表現するにはあまりにも恐れ多いと考えたのでしょう。日本に神像がないのは当然なのです。
そこで皇祖神は依り代(神が出現するための媒体)いう形で表現したのです。
例えば、伊勢神宮の「鏡」、熱田神宮の「草薙の剣」、宮中に存在する「勾玉」の「三種の神器」(アマテラスが孫のニニギに授けた宝物)は神の依り代とされています。
だから仏教が日本に入ったとき、人々は驚いたに違いありません。
元々、神道には教義・神像がないので、経典と仏像を目にしたとき、文化のあまりの違いに驚かなかったはずがありません。
神道に教義がないのは、キリスト教・仏教等の「道徳とか愛」は日本人の常識であり、争いのない日本人には必要のない教義だったからです。
“お天道様が見ている”
これが究極の日本人の「道徳心」だったのです。
日本人は、自然に恵まれているので自然環境を変える必要性はなく、自然のルールに従い、自然をそのまま受け入れることが神(自然)への信仰だったのです。
中山恭三(なかやま きょうぞう)/不動産鑑定士。1946年生まれ。
1976年に㈱総合鑑定調査設立。 現在は㈱総合鑑定調査 相談役。
著書に、不動産にまつわる短編『不思議な話』(文芸社)を2018年2月に出版した。